デリバリーロボット8選。自動配送の実用性や活用シーンを紹介
最終更新⽇:2025-05-22

デリバリー業務における配達効率の向上や、配送コストの削減にお悩みの物流・配送担当者の方へ。デリバリーロボットの仕組み活用シーンに加え、実用化が進む注目モデルを紹介します。
目次
デリバリーロボットとは?
デリバリーロボットとは、商品や荷物を人の手を介さずに自動で配送するロボットのことです。「自動配送ロボット」や「配達ロボット」とも呼ばれており、GPSやAI、各種センサーを搭載し、指定された目的地まで自律走行で荷物を運びます。
デリバリーロボットの社会実装は政府でも推進の動きが高まっており、実用化に向けた法整備も進んでいます。2023年4月1日に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」によって、一定の大きさや構造の要件を満たすロボットであれば、事前の届け出によって公道での走行が可能になりました。
今後、技術の進歩とともにデリバリーロボットの実用化が進み、更に多様なシーンでの活用が期待されるとともに、人手不足の解消や物流の効率化、特にラストワンマイルの問題解決に期待が集まっています。
自動配送ロボットの安全性は?
ロボットデリバリーの導入にあたり、最も懸念されるポイントのひとつが安全性です。安全基準の確立と遵守は、デリバリーロボットが社会に受け入れられるために重要な要素といえるでしょう。
現状においては、ロボットデリバリー協会によって定められた安全基準が存在しており、これに適合したロボットのみが公道を走行可能となっています。
この基準には、以下のような項目が含まれています。
| ロボット本体の大きさや重量の上限 | 法案に定める遠隔操作型小型車の基準に適合することが前提とされています。 |
|---|---|
| 適切な速度での走行 | 最高速度の制限が設けられています。 |
| 非常停止装置や衝突回避機能の搭載 | 緊急時の停止や障害物との衝突を避けるための機能が求められています。 |
| 事故や障害物への対処を想定した遠隔監視システムの整備 | ロボットの運行中には、遠隔地からの監視が行われ、異常時には適切な対応ができる体制が求められています。 |
こうした取り組みにより、デリバリーロボットの安全性は段階的に高められています。
デリバリーロボットの価格は?
デリバリーロボットを導入するにあたって必要なコストとしては、主に初期費用と運用費用が想定されます。
初期費用の内訳としては、ロボット本体を購入する費用のほか、導入予定エリアの地図データを作成し、最適な配送経路を設定するための準備費用が必要になります。また、ロボットの充電や待機スペースの確保、テスト走行を行うための費用など、諸経費の考慮も必要です。
代表的なデリバリーロボットの例として、無人宅配ロボットの「DeliRo」導入費用を見てみましょう。
- 運用費用:月12万円/台~(5年リース)
- 初期費用:200万円~(実証実験費用)
DeliRoの場合、運用費用として月額約12万円~、初期費用としては200万円程度が必要になるケースが多いです。ただし、購入するロボットのモデルや導入規模、運用の複雑さによって総額のコストは大きく異なるため、より具体的な費用を知りたい場合は、個別の見積もりが必要です。
購入だけでなく、リースやレンタルといった利用方法が用意されている事業者もあるため、自社の状況に応じて柔軟に選択肢を検討すると良いでしょう。
デリバリーロボットの仕組み
ここからは、デリバリーロボットの仕組みについて、運転方法やユーザーの利用方法の観点から解説します。
車両の運転方法
デリバリーロボットには、主に「自動配送」と「遠隔操作」の二つの運転方法が存在します。
自動配送の場合
自動配送の場合、デリバリーロボットは導入エリアのマップデータに基づいて自動的に配送ルートを作成します。この際、配送にあたって最適な経路を見つけ出すためのチューニングや、複数回のテストを導入前に行うのが一般的です。
入念な事前準備で十分なチューニングがなされていれば、ロボットは人の手を介さず、自律して目的地まで荷物を運搬できます。
遠隔操作の場合
遠隔操作による運転方法では、人間が遠隔地からデリバリーロボットを操作して目的地まで荷物を配送します。導入エリア周辺の安定的な通信状態を確保しておき、オペレーターが遠隔地からロボットを操作して配送を行うイメージです。
遠隔操作の場合、自動配送とは異なり、デリバリーロボットの導入に際して周辺の3D地図等の詳細な準備が不要になるというメリットがあります。配送エリアに未知の障害物が想定される場合や、複雑な道路状況の中を配送しなければならない場合に特に有効です。
ユーザーの利用方法
- 商品を注文する
- デリバリーロボットが目的地に到着する
- デリバリーロボットの扉を開ける
- 中の商品を受け取る
ユーザーがスマホやタブレットを通じてアプリや専用サイトから商品を注文すると、デリバリーロボットが指定された目的地へ配送を開始します。
目的地に到着すると、ユーザーのもとに通知が届くため、ロボットが商品の配送に訪れたことを把握します。通知を確認したら、到着したロボットの扉を暗証番号やQRコードの読み取りなどで解錠して、中の商品を受け取るだけで利用は完了です。
デリバリーロボットの活用シーン
デリバリーロボットの主な4つの活用シーンと、期待されるメリットを紹介します。
1.フードデリバリー
飲食店から顧客への食品配送を自動化するデリバリーロボットの存在は、配達員不足解消の手段として重要な役割を担い始めています。
たとえば、2024年3月6日から東京都日本橋エリアで開始されたロボットデリバリーサービス(Uber Eats Japan、三菱電機、Cartkenの3社が合同で提供)は、Uber Eatsで注文された商品を人間ではなくロボットが配送するという試みです。
2.日用品や医薬品の宅配
日用品や医薬品の宅配も、デリバリーロボットの重要な活用シーンとして期待されています。ロボットは夜間や悪天候などの人間が働きにくい環境下でも商品を迅速に配達することが可能。また、非対面でのやり取りにより、感染症対策の面でもメリットがあります。
3.移動販売
移動販売におけるデリバリーロボットの活用は、まだ実験段階にありますが、将来的には日常的な買い物が難しい人々へのサポート手段として期待されています。キャッシュレス決済に対応した移動販売ロボットも実用化に向けて検討が進められています。
高齢者や身体の不自由な人だけでなく、仕事や育児などの都合で自宅を離れることが難しい人でも、室内にいながら買い物ができるというメリットもあります。
4.搬送業務(屋内)
ホテルや病院、オフィスなどの屋内環境でも、デリバリーロボットは活用されています。
たとえば、ホテルではアメニティの客室配送をロボットが担うことで、スタッフの業務負担を軽減し、サービスのスピードアップにもつながります。ロボットがエレベーターに自動で乗り込み、階をまたいで荷物を届けるなど、柔軟な運用が可能です。
デリバリーロボットのタイプ
デリバリーロボットは、主に「屋外向け」と「屋内特化型」の2タイプに分類されます。用途や導入場所に応じて、最適なタイプを選ぶことが重要です。
1.屋外にも対応するタイプ
屋外にも対応するタイプのデリバリーロボットは、公道を走行できる基準を満たしており、主にフードデリバリーや一般の宅配サービス、移動販売などに適しています。
1-1.フードデリバリー・宅配向き
フードデリバリーや宅配サービスなどに向いているタイプのデリバリーロボットは、小型かつ低速度で運行する機種が多く、公道を走行することを考慮して安全性にも配慮された設計が特徴的です。
たとえば、「DeliRo(デリロ)」は、カメラやレーザセンサーで周囲環境を360 度認識しながら最大時速 6km で自動走行。運ぶ荷物の大きさや形状に応じて1 ボックス、4 ボックス、8 ボックスを選択でき、積載量は最大 50kg に対応しています。
Uber Eats アプリ上で展開される、Cartken 製のデリバリーロボットは、内部に断熱性のある約 27 リットルの積載スペースを搭載。適切な温度を保って料理などを配達できるようになっています。
1-2.移動販売向け
移動販売に適したデリバリーロボットは、フードデリバリー向けの機種とは異なり、大型かつ高速なものが多い傾向にあります。異なるサイズの複数のロッカーを搭載しており、様々な商品を積み込んで配送できるように設計されています。
現状、移動販売用のデリバリーロボットは実証段階にあり、日本国内で実用化はされていませんが、将来的には実用化されていくことが想定されます。
京セラコミュニケーションシステム株式会社は、2022年に温冷蔵機能を備えた無人自動走行ロボットが公園やマンションなどを周回して移動販売を行うサービスの実証実験を実施。技術検証を重ね、地域を拡大してサービスを実現できるよう取り組んでいます。
2.屋内に特化
屋内用のデリバリーロボットは、主にホテルや病院、オフィスビルなど室内で使用することを想定しています。狭い廊下や人の多い環境でも効率的に動けるよう設計されており、物資の運搬をスムーズに行えます。
運搬時の安全性が重視されるため、一般的には速度が控えめに設定され、人や物に対する配慮がなされています。
こちらのタイプに該当する「Relay」は、「品川プリンスホテル」では、「S-mile(スマイル)」の愛称で導入されており、障害物を避けながら自動移動して、宿泊客の部屋までアメニティなどを届けられます。
主なデリバリーロボット(フードデリバリー・宅配向き)
DeliRo(デリロ)(ROBO-HI株式会社)

(出所:DeliRo公式Webサイト)
荷物を積載し、自動運転技術を駆使して公道を移動することが可能な無人宅配ロボット。公道走行時の最大積載量は50kgで、1ボックス、4ボックス、8ボックスの3種類から用途に応じて選択できる。
また、視覚と音声によるコミュニケーション機能を備えており、利用者や周囲の人々との交流が可能であることから、見回りなどにも活用が期待される。日用品の配達や医薬品の宅配、移動店舗、クリーニングの集配など、多岐にわたる用途に適応する設計となっている。
- 料金:月額12万円/台〜、初期費用200万円~
Cartken(Cartken Inc.)
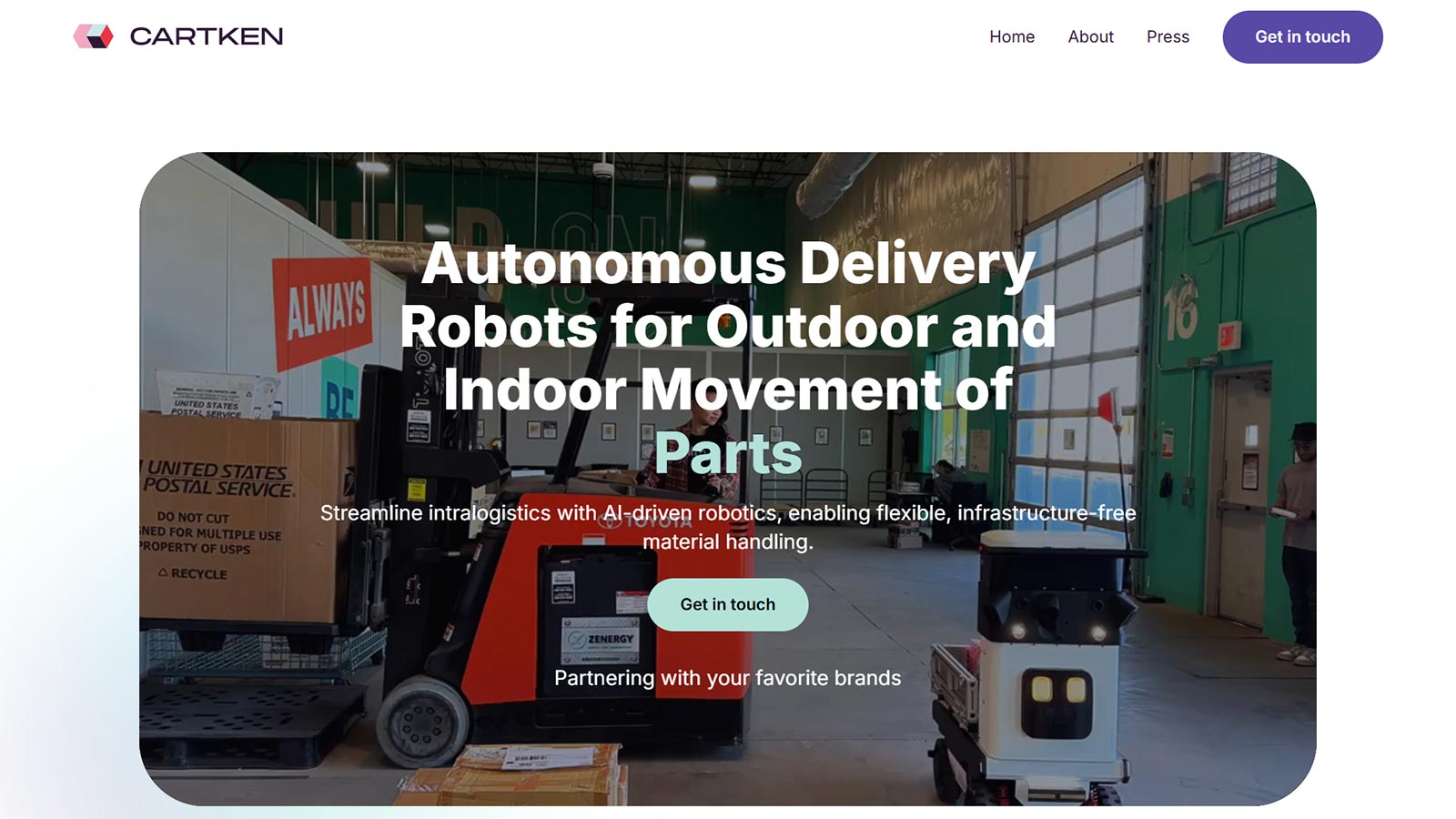
(出所:Cartken公式Webサイト)
米スタートアップ開発の自動配送ロボット。Uber Eats Japan、三菱電機と業務提携を結び、2024年3月からAIを活用した自律走行ロボットによるデリバリーサービスを提供している。東京都・日本橋エリアの2店舗で食事の配達を開始しており、順次エリアを拡大していく予定。
人手不足の解消と配送手段の多様化を目的としており、配送中の食品を適切な温度で保つ機能を備えるほか、顧客のプライバシーにも配慮されている。
- 料金:要問い合わせ
LOMBY(LOMBY株式会社)

(出所:LOMBY公式Webサイト)
国内の自動車メーカーと駆動部・車体を共同開発した国産の配送ロボット。24時間体制で低コストの配送を提供し、天候に左右されずにサービスを実施できる点がメリット。これにより、新たなラストマイル配送インフラの構築を目指している。
屋外は遠隔操作での走行になるため、事前に周辺の3D地図等の準備は不要。導入先周辺の通信状況の確認のみで導入が可能となっている。屋内を配送する場合には自律走行にも対応。
- 料金:要問い合わせ
Hakobase(株式会社Hakobot)

(出所:Hakobase公式Webサイト)
2018年5月宮崎県で設立されたロボットメーカーによる配送ロボット。「なんでも載せられる、しっかり運ぶ」をコンセプトに開発され、走行ユニットである「Hakobase」のみで自動運転実装が可能。
荷室は用途に応じてカスタマイズしたものを取り付けられるセパレート設計になっており、配送以外にも大型備品の運搬など幅広いシーンで活用できる。パワフルな走りを実現する4輪駆動(4WD)と小回りの利く4輪操舵(4WS)をかけ合わせた走破性も特徴。自動運転システムについてはSLAM技術を採用している。
- 料金:要問い合わせ
主なデリバリーロボット(移動販売向け)
自動配送サービス(京セラコミュニケーションシステム株式会社)
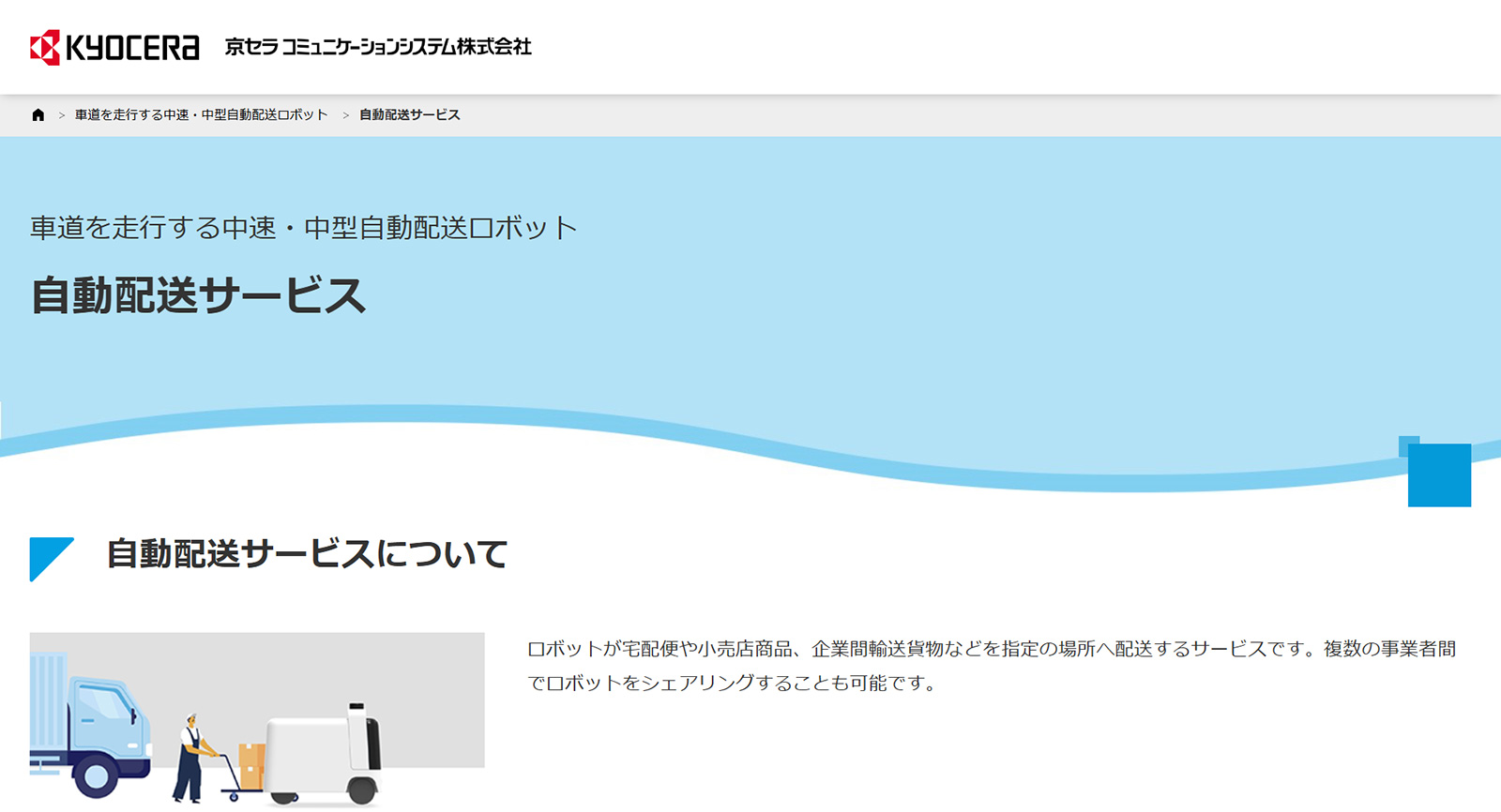
(出所:自動配送サービス公式Webサイト)
車道を走行可能な中速・中型の自動配送ロボットを活用し、宅配便や小売店の商品、企業間の貨物などを指定の場所へ配送するサービス。ロボットのシェアリング運用にも対応しており、複数の事業者で効率的に利用できる点が特長。
北海道石狩市では、ヤマト運輸と連携した個人向け配送実証のほか、地域内事業者によるロボット共用型の配送実証なども実施。スマホやタッチパネルによるロッカー操作で、非対面かつスムーズな荷物の受け渡しを可能にしている。
今後は、温冷蔵ロッカーを備えた移動販売や、店舗購入品の自宅配送を支援する買い物支援サービスとしての展開も視野に入れている。
主なデリバリーロボット(屋内特化)
Relay(Relay Robotics, Inc)
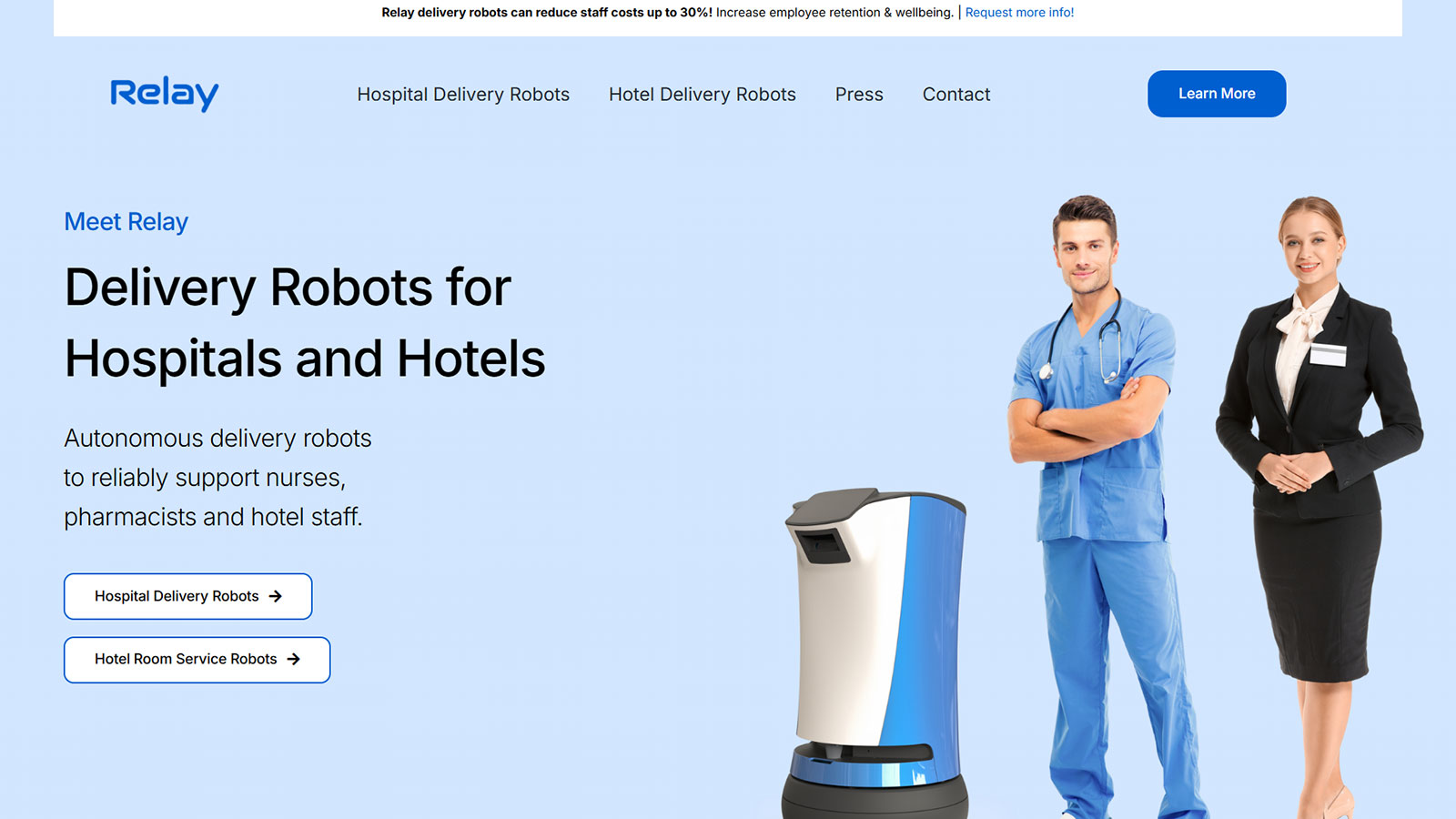
(出所:Relay公式Webサイト)
ヘルスケアやホスピタリティ業界でのスタッフ支援に貢献する自律型サービスロボット。ゲストとスタッフのやり取りをスムーズにし、業務の効率を高めることで、サービスのパーソナライズ化とゲスト満足度の向上を実現している。
2024年3月現在、品川プリンスホテルや渋谷ストリームエクセルホテル東急などで導入されており、ルームサービスの配達や情報提供など、シームレスかつコンタクトレスな体験が評価されている。
- 料金:要問い合わせ
GoGo(GlobalView Technology合同会社)

(出所:GoGo公式Webサイト)
ホテル、病院、オフィスビル、工場などで非接触配送を行う自律走行型ロボット。2つの収納スペースを持ち、UV除菌機能を備え、安全に物を運ぶことが可能。
狭い場所や斜面などの悪環境にも対応可能で、障害物を避けながら最適ルートを自律走行し、充電も自動で行える。大容量でありながらコンパクトで、安全性と効率性を兼ね備えているのも特徴。
- 料金:要問い合わせ
MELDY® (メルコモビリティーソリューションズ株式会社)

(出所:MELDY®公式Webサイト)
病院向けに提供される自律走行型の搬送ロボットサービス。薬剤や検体、注射薬カートの運搬に対応した「MELDY®」を中心に、施設環境に応じた導入支援・保守サポートを含むトータルソリューションを展開している。
ロボットはLiDARやカメラによる障害物回避、ICカード解錠、履歴管理、エレベーター連携などに対応し、安全かつ非接触の搬送を実現。開発中の「MELCADY®」では、注射薬自動払出システムと連携したカート搬送にも対応予定。
搬送業務の省力化とスタッフのタスクシフトを支援し、医療現場の業務効率化と感染対策にも貢献する。
まとめ
GPSやAIを活用し、人の介入なしで目的地まで荷物を運搬できるデリバリーロボットは、物流効率化や配送コスト削減を目指す事業者にとって有望な技術です。
食品配送、日用品や医薬品宅配、移動販売、屋内搬送業務など、多岐にわたるシーンでの活用が可能であり、現段階では実証実験にとどまっている分野でも、将来的に幅広い活用が期待されています。
道路交通法の改正に伴い、公道走行が可能となったことで、特にラストワンマイル配送の効率化において期待が高まっています。
導入を検討する際は、導入コスト、安全性、活用シーンに応じて、適切なタイプやモデルを選定しましょう。






